屏風 (びょうぶ)
| 以前は、装飾や風除け(かぜよけ)に常用され、また慶弔の際に使われるなど、 |
| 家庭でよく見られた屏風(びょうぶ)。 |
| |
| 和室が少なくなったり、冠婚葬祭が会場で行なわれるようになって、 |
| 屏風が使われることが少なくなってきたように思われますが、 |
| 和の空間・和みの空間を演出する屏風の人気が高まってきています。 |
| |
| 金地に絹を貼った下地や和紙に描いた、山水画や風景画・源氏物語絵・など、 |
| 洋風の造りにもよく合いますので、洋室や玄関に屏風を飾る方が多くなっています。 |
| サイズによって |
本間屏風 |
( ほんけんびょうぶ ) |
|
利久屏風 |
( りきゅうびょうぶ ) |
|
三尺屏風 |
( さんじゃくびょうぶ ) |
|
棚下屏風 |
( たなしたびょうぶ ) |
|
| などと呼び、屏風を構成する面の数によって |
|
二曲、四曲、六曲などと呼びます。 |
風景画などは「遠藤晃」の名で、源氏絵や花鳥画は「柴田春慶」の名で描いています。
本間二曲屏風(高 173cm x 幅 188cm)
お部屋の角に置いて飾る屏風です。
この屏風は、洋室よりも和室の方が合う印象です。
鴨居近くまで高さがあり、幅も広いので、八畳以上の部
屋に最適です。
|
|
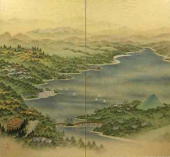
屏風「近江・湖西図」 |
|
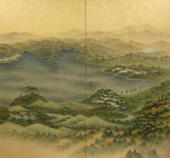
屏風「近江・湖東図」 |
|

屏風「青緑山水」 |
|
|
|
|
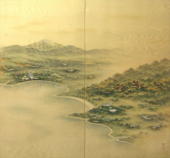
屏風「長浜〜湖東三山」 |
|

屏風「近江八景(墨)」 |
|

屏風「青松山水」 |
|
|
|
|
利久二曲屏風(高 153cm x 幅 144cm)
六畳から使える、高さ約150cmほどの大きさの屏
風です。
部屋のコーナーに置いたり、間仕切りに使ったり、
スペースがあれば玄関に使われることもあります。
フローリングや板敷きの床に置くと、畳の部屋とは
違った趣があります。
|
|

屏風「近江八景」 |
|
|
|
|

屏風「松に鶴」 |
|

屏風「湖東三山」 |
|
|
|
|

屏風「彩色山水」 |
|

屏風「孔雀」 |
|
屏風「青緑山水」 |
|
|
|
三尺四曲屏風(高 92cm x 幅 180cm)
高さ三尺(約90cm)広げると幅が六尺(約180cm)
と、畳とほぼ同じ大きさで、四曲屏風の中で最も使い
やすい大きさの屏風です。
絵によっては、四面のうちの片側の二面を折り畳むと
二曲として使うこともできます。
風屏を広げて壁に取り付けると独特の風合いとなり
好評です。
また、従来の屏風使用目的の一つである目隠しとし
てもよく使われますし、風除けとしても冷気の沈み込
みを防ぐので布団でお寝みになる方には重宝なもの
です。
 の形に置くのが一般的なのですが、中央を奥に の形に置くのが一般的なのですが、中央を奥に
やって、 の形に置くと、屏風の前にお雛様や焼き の形に置くと、屏風の前にお雛様や焼き
物など、お好きなものを飾ることができます。
|
|

屏風「朱塔」 |
|

屏風「善通寺」 |
|
|
|
|
|

屏風「源氏(関屋・花宴)」 |
|

屏風「源氏(須磨・初音)」 |
|

屏風「源氏(行幸)」 |
|
|
|
|

屏風「源氏(関屋)」 |
|

屏風「源氏(胡蝶)」 |
|

屏風「紅葉に芙蓉」 |
|
|
|
|
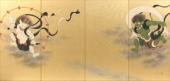
屏風「風神・雷神」 |
|

屏風「オランダ船」 |
|

屏風「波に鷺」 |
|
|
|
|
近江風景

屏風「近江八景」 |
|

屏風「近江八景(墨)」 |
|

屏風「紫式部と近江八景」 |
|
|
|
|

屏風「湖東三山〜三上山」 |
|
|
|
|
|
|
京都風景

屏風「醍醐」 |
|

屏風「嵐山」 |
|
|
|
|
|
奈良風景

屏風「当麻寺と二上山」 |
|

屏風「斑鳩三塔」 |
|

屏風「古都望見」 |
|
|
|
|
棚下四曲屏風(高 65cm x 幅 176cm)
床の間の横の飾り棚の下が空間になっている造りのお座敷で、飾り棚の下に入れて飾るように作られた屏風です。
高さが低く圧迫感がないため、玄関などにもさりげなく置くことができます。
洋室ではサイドボードの上に置くこともでき、三尺四曲屏風と同じく の形にすると、屏風の前にいろいろなものを飾ることができます。 の形にすると、屏風の前にいろいろなものを飾ることができます。
|
|

屏風「古都望見」 |
|

屏風「四季花鳥」 |
|

屏風「紅白梅に流水」 |
|
|
|
|

屏風「春秋山水」 |
|

屏風「古都望見」 |
|

屏風「四季山水」 |
|
|
|
|

屏風「水墨山水」 |
|
|
|
|
|
|
仕様について
| 中金箔仕様 |
本金箔が高価なため、代わりに用いる箔です。 |
|
代用金・洋金と呼ばれる箔も同種です。 |
|
落ち着いた雰囲気を出すために古色をつけています。 |
|
|
| 絹裏箔仕様 |
明るい中金箔の上に薄い絹を1枚貼ったものです。 |
|
箔の反射光が押さえられて、見た目に優しくなります。 |
|
また、絵の具の発色も柔らかくなり、しっとりとします。 |
|
|
| 二枚絹裏箔仕様 |
明るい中金箔に薄い絹を2枚重ねて貼ったものです。 |
|
モアレという木目のような模様が現れて、 |
|
画面に動きや奥行きが生まれます。 |
|
この上に風景を描くと、遠景では霞がかかったような効果が |
|
得られるなど、その特色が生かされます。 |
|
絵の具の発色も絹独特の柔らかなものになります。 |
|
|
| 鳥の子紙仕様 |
日本画用の手漉きの和紙です。 |
|
真っ白でなく、生成りのようにクリーム色が入った、 |
|
目に優しい色の紙です。 |
|
|

|